(三、"証拠の標目"は割愛する)
【狭山事件第一審判決】
四、弁護人等の主張に対する判断
(一)自白調書の証拠能力について
弁護人=中田直人、同=石田亨は、本件昭和三十八年七月九日起訴にかかる強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂の事実についての被告人の司法警察員及び検察官に対する供述調書は、いわゆる別件逮捕再逮捕による逮捕勾留の蒸し返しによる違法、不当の拘禁中の取調べによって得られた供述に基づくものであるから、違法な証拠であり証拠能力を否定さるべきものであると主張する。
よってまずこの点につき考察するに、記録によれば被告人は昭和三十八年五月二十三日窃盗、暴行の件、本件恐喝未遂の被害事実に基づく逮捕状により逮捕され、同月二十五日右被疑事実に基づく勾留状により勾留され、同年六月十三日まで右勾留が延長されたうえ、同日窃盗、森林窃盗、傷害、暴行、横領被告事件につき、浦和地方裁判所川越支部に起訴され(同被告事件は、同年七月十七日、浦和地方裁判所第一刑事部において、本件同庁昭和三八年《わ》第二七四号、強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂被告事件に併合審判の決定がなされた)、右六月十三日右起訴事実中、前記勾留の起訴となった事実以外の窃盗、森林窃盗、傷害、暴行、横領の事実についても勾留状が発付されたが、弁護人=石田亨、同=橋本紀徳からの請求により、同月十七日前記川越支部裁判官により保釈許可決定がなされた。ところが右保釈許可決定の執行後間もなく、強盗強姦殺人、死体遺棄の被疑事実に基づく逮捕状より即日再び逮捕され同日二十日右被疑事実に基づく勾留状により勾留され更に同年七月九日まで右勾留が延長されたうえ、同日、本件強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄恐喝未遂被告事件につき浦和地方裁判所に起訴されるに至ったことが明らかである。
ところが、もし捜査機関において、当初の逮捕状及び勾留状に記載されている被疑事実について取調べの意図がなく、専ら本来の目的とする事件の捜査の必要上該逮捕、勾留を利用するため、名を別件に藉(か)りてこれを請求したのであれば、それはまさに別件逮捕及び勾留として違法であり、第二次の逮捕、勾留もまた違法、不当なものといわなければならない。
しかしながら本件においては、記録を検討すれば当初の窃盗、暴行、恐喝未遂事件について為された前記逮捕及び勾留は、捜査機関が主として該逮捕、勾留の基礎となった窃盗、暴行、恐喝未遂及びその頃発覚するに至った前記六月十三日起訴に係る事実中、同日勾留状の発せられた各罪についての取調べに利用したものであることが認められるのであって、決して前記中田、石田両弁護人の主張の如く、最初から、専ら当時未だ逮捕、勾留をなし得る程度の資料を具備していなかった前記強盗強姦殺人、死体遺棄事件を取調べる目的で請求し、且つ右取調べに利用したものとは認められない。もっとも第一次の逮捕、勾留の期間中において、右恐喝未遂に使用された脅迫状の筆跡を調べた結果、それが被告人の作成したものと認められたため、その文面から中田善枝の殺害にも関係あるものとして、被告人から煙草の吸殻と唾液の任意提出を求めて血液型の鑑定の嘱託をする等、右殺害等事件についても取調べをしたことが窺われるが、たとえ逮捕、勾留の基礎となっていない事実であっても、たやすく発覚するに至った前記余罪についてはもちろん、いやしくも恐喝未遂に関連する右殺害等について、右程度の取調べをすることは何ら法の禁ずるところではないと思料されるから、これが取調べをしたからといって直ちに請求窃盗等についてなされた第一次の逮捕、勾留が当初から前記強盗強姦殺人事件の捜査に利用されたものと為すことはできず、従って右逮捕、勾留を目にして違法、不当なものと為すことはできない。果たしてしからば(注:1)、その後において、前記強盗強姦殺人死体遺棄事件につき発せられた第二次の逮捕状及び勾留状に基づく逮捕、勾留は、何ら逮捕、勾留の蒸し返しということではできないから、これまた違法、不当なものということはできず、その期間中に作成せられた本件強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂の事実についての被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書の証拠能力も、その故を以って(注:2)これを否定することはできないのである。しかも、本件において強制、拷問、脅迫その他供述その他性を疑わしむるべき事実は毫(注:3)も存しないのであるから、前記両弁護人の主張は採用できない。
*
注:1「果たしてしからば」=その言葉のとおりであるならば。もしそうならば。
注:2「故を以って(ゆえをもって)」=ゆえに。〜を理由として。
注:3「毫(ごう)」=少しも。ちっとも。いささかも。
*
◯もし、あくまでも『もし』であるが、本件の真犯人が存命でありその人物が自首した場合、これはどういう展開をみせるのかなどと考えていたところ、この疑問に類似する記述を見つけた。
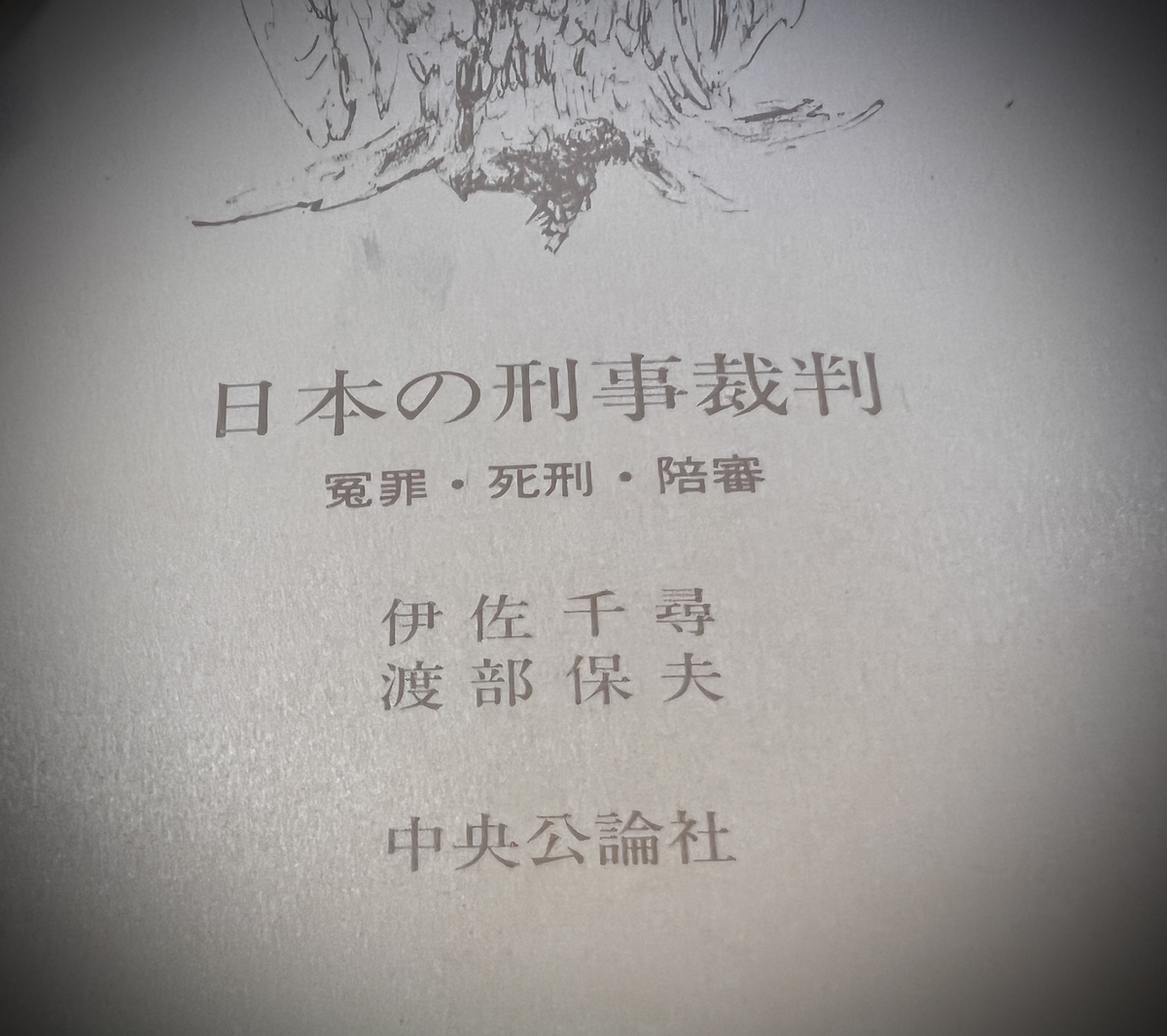
(『日本の刑事裁判 冤罪・死刑・陪審』中央公論社 全500頁)
この書の第七章に、「真犯人が出ても覆らない有罪判決」という恐ろしい項目がある。少し触れてみよう。
「昭和二十七年、東北の某所でA子という女が殺害された。そこでBという男が逮捕、起訴され、一、二審で懲役十年の有罪判決が下された。控訴するも棄却され上告を断念、刑務所へ服役する。
ところが十四年後の昭和四十一年、Cという男が真犯人として名乗り出た。東京地方検察庁が調べるとこの男が真犯人であることが判明し、当然であるが強盗殺人罪でこれを起訴した。しかしながら東京地方裁判所では証明が不十分だとし、Cを無罪とした。検察官は東京高等裁判所に控訴するが、間もなくCは自らの命を絶った。結局このCの件はうやむやな形で終わってしまう。こののち、Bは再審請求を行ない仙台高等裁判所が再審の開始を決定、Bは無罪となったが、国家賠償請求は一、二審ともに棄却され、上告を断念している(刑事補償は受けている)。六十六歳を迎えていたBは次のコメントを残している。『裁判所はもう信用できない。訴訟費用もかかり、苦しむのは自分だけ。早く事件のことは忘れたい』」(あれ、有罪判決は覆っているぞ)
Bに対する国家賠償請求の棄却について東京高裁は「Bを間違って有罪にし刑務所へ入れてしまったが、警察にも検察官にも裁判所にも過失はなかった。したがって請求を棄却する」と述べている。
この東京高裁の論理で冒頭の我が疑問を考えると、真犯人が現われた(あくまで仮定の話)ことにより、これが犯人と認められた場合、石川一雄被告の汚名は晴らされることは間違いなく、自首をした真犯人は起訴されることとなろうが、石川一雄被告に罪を着せその人生を微塵に破壊したにも関わらず、国側は過失を一切認めないという事態を招きかねない。
石川一雄被告の自白(調書)は虚偽であるとの見方がこの事件を知る人々のあいだで囁かれるが、この虚偽の自白をさせた警察官、検察官らには重い過失が発生し、さらにその自白の虚偽性を見極められなかった裁判所には、より重度の過失があると言えよう。ところが誤判であったという事実を突きつけられたとき、「いや、私としてはあの時、精一杯やったんです。あの時点での証拠によれば、あの判断が妥当だったんです」と彼らは詭弁をもてあそび、自らの過失は一切ないと背を向けるのであろう。
『もしも』ということで、仮定の疑問を発想し、その疑問の答えを考えてみたが、文章の腰は折れ曲がり、そのまとまりもなく何を書きたかったのかさえ忘れ、本日も時間を無駄にする。