【公判調書3131丁〜】
「第五十八回公判調書(供述)」
証人=高村 巌(六十一歳・文書鑑定業)
*
橋本弁護人=「昭和三十四年からですか、文書鑑定研究所を創立されたのは」
証人=「三十三年秋でございましたね」
橋本弁護人=「これはあなたが所長で」
証人=「まあ、そういうことになりますね」
橋本弁護人=「会社組織か何かですか」
証人=「いや、ただそういう名称だけで、法的なものは施(ほどこ)してございません」
橋本弁護人=「所員という人はどういう人を採用したんですか。やはり専門家ですか」
証人=「まあ半分専門家ということですが、まあ専門家というほどのものでもございませんね。ただアシスタントとして手伝うくらいなもので、主として私がやっておったんです」
橋本弁護人=「創立してから何か筆跡鑑定について研究をしたことはあるんですか」
証人=「科学的に筆跡鑑定をやるべく、今までは経験の世界でやっておりましたが、科学的にやるべく、出来るだけ科学的にということで研究をいたしましたが、非常にその本当の意味での科学的ということになると、厳密な意味での科学的ということになるとむずかしい問題がたくさんございます。その研究をいたしました」
橋本弁護人=「今、非常にむずかしいと仰いましたね、これはどの点がでございますか」
証人=「これは人間が書く文字というものは印刷の字とは違いまして、書くたびに少しずつ厳密な意味において変化していくわけです。一度書いた文字を二度目に書けるかというと、厳密な意味では角度がいくらか違いますし、また、震えが出て来たり、傾斜が変わったり、いろいろな意味で多少変わって来る、その中から特徴を掴んでいくということで、それを分類して一つの特徴を出すことが、機械的に出していくということが非常にむずかしい。純粋に科学的という以上は、これは真に科学的という以上は専門家を必要としないんです。誰がやってもそのメソードについて方法によってやっていくならば、同じ結論が出なくちゃいけないというのが本当の科学的であって、もっと煎じ詰めれば、いわばボタンを一つ押せば答えが出てくるというところまでいかなければ真の科学的とは言えないと思います。今、科学的、科学的と言われているものの中でも、私から言わせれば科学的でないものがたくさんあります。どんな電子計算機を使おうが推計学を用いようが、最後には人間が判断しなければならないという問題があるわけです。例えばにわとりの雄雌を、卑近(ひきん)な例ですが、ひよこのうちに識別することにしても、科学的にいうならばもっと厳密な科学的識別法があるんでしょうけれども、これはやはり経験によらないと分からない。ひよこの尻をちょっと見て専門家は雄雌を完全に識別しております。ところがその方法を科学的にいろいろ教わっても、その息子がやった鑑定が、親から受け継いで本当の奥の手を聞いておる筈の息子がやってもみんなは当たらず、間違ってしまうということで、やはりこれは非常に経験の世界があると思うんで、またいろいろの分野についてみましても、あるところまでは科学的な機械を使い科学的な方法をやりましても、最後の断を下すのはやはり専門家が必要である、その鑑定を下さなければならない、そこで科学的でないという、多少、主観が入って来るんじゃないかというようなことがあるわけであります」
橋本弁護人=「そうしますと、あなたの仰る意味は少なくとも従来の筆跡鑑定の方法は科学的であったとは思われないと」
証人=「完全科学的じゃないと思います」
橋本弁護人=「やはり経験を積んだ人の体験に基づいての判断」
証人=「経験に基づく判断によって成されて来たと」
橋本弁護人=「あなた自身の鑑定方法はどうなんでしょうか、科学的にするために研究をなさったと言われましたが」
証人=「やっておりますけれども、まだ完全に科学的というところまではいっておりません。これは未科学であって非科学ではありません。この経験によってやっておるというより他に方法がないと思います」
(続く)
*
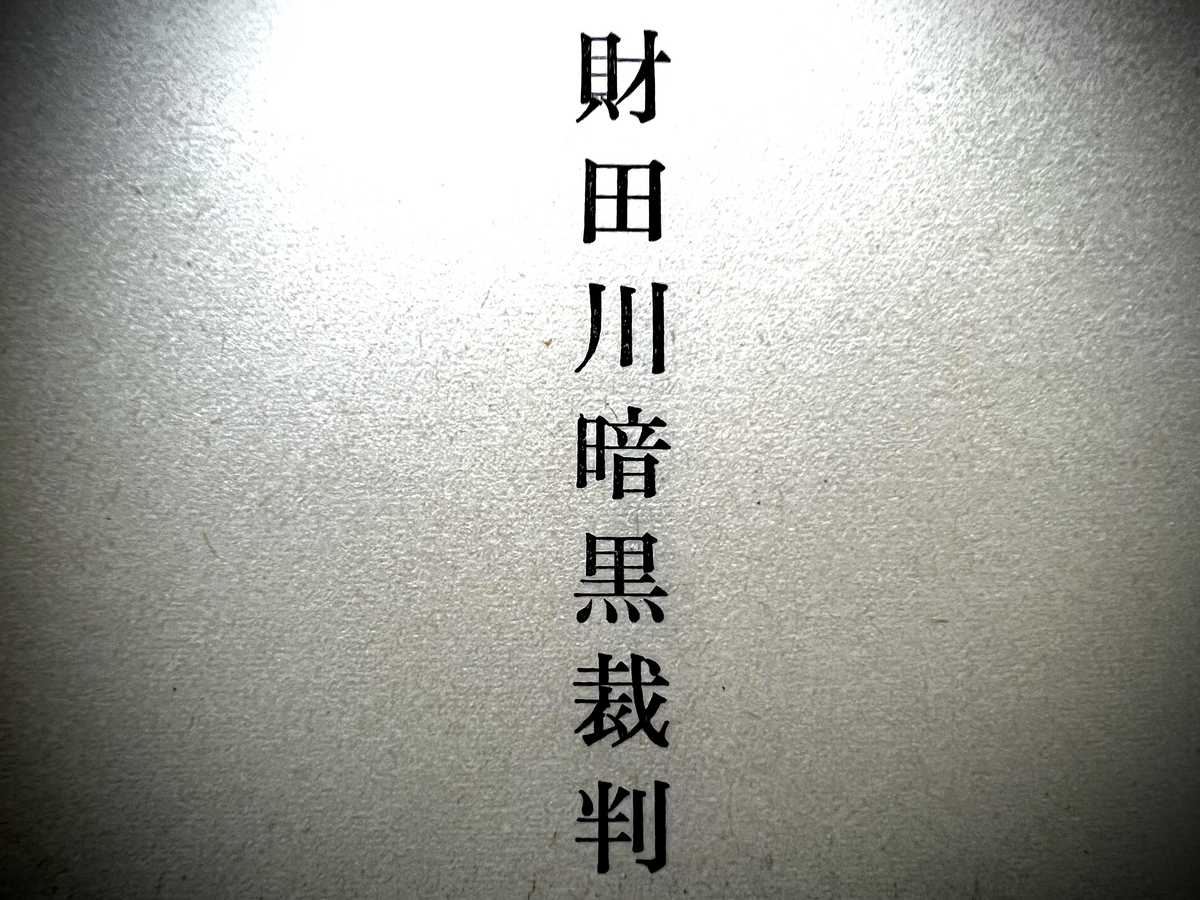
○昨日の流れから、私は久しぶりに「財田川暗黒裁判・矢野伊吉著」を再読した。読み進めるうちに、今現在、裁判所が狭山事件の再審へ向けた動きを全く見せないという事実、その理由の一つが垣間見えると思える記述を見つけた。一部抜粋する。
『もし、谷口(死刑囚)と出会うことがなければ、私は老判事として円満に退職し、老妻とお茶を呑みながら、裁判官としての人生を懐かしく想い起こしていたことだろう。
略
〜私が知ったことはあまりに重大なことであり、あまりに異常なことだった。これが運命だとしても、それはあまりにも苛酷すぎる。あれほどまでに裁判官の仕事を愛していた私が、警察に、検察庁に、そして裁判所に、さらには法務省にまで、疑惑を持ち、批判するようになってしまったのである。
その頃、私は家に持ち帰った書類を前にして頭を抱えていた。「どうすればいいのか」私はその処理について悩んだ。
しかし、裁判官として採るべき道はすでに決められている。ただ法にしたがうのみなのだ。あることをあると認定する。事実を事実として判定する。それだけのことだ。もし、私がこのことによって、もはや三界に身を置くことができなくなったとしても、それは、まったく無実にして死刑の執行におびえている谷口の運命にくらべたなら、取るに足らぬことだと思えた。
谷口の無罪を証明することは、とりもなおさず、警察官を、検事を、先輩の裁判官の落ち度を摘発し、それを暴いてしまうことになるのだ。私といえども、世の人びと同様、名利を欲し、立身出世を望むことには変りはない。ただ、不正義に気付いてしまったなら、気付いた人間がやはり何かをしなければならないのだと思った』(財田川暗黒裁判より)
*
○ことさら矢野伊吉という堅物裁判官判事ですら、先輩の裁判官らの落ち度を暴くことには気が引ける思いがあったということがうかがえる。いわゆる、忖度であるが、狭山再審に置きかえれば、悪いしきたりには従わない矢野伊吉のような人間が現在の裁判所に不在であることが再審請求を阻む要因となってはいないだろうか。
ここでもう一つ抜粋しておきたい記述がある。矢野伊吉自身が受けた「圧力」についてである。
『谷口の無実を主張する私に対して加えられる圧迫は表現し難いものがある。私は第二審以来、谷口の弁護人として抗告趣意書を提出しただけで、事実、その報酬は誰からも、またどこからも一銭たりとも受けてはいない。それにもかかわらず高松弁護士会は、私に対して懲戒処分に付すなど、その狂乱ぶりはひどい。無実の谷口に死刑の宣告を与えるほどの実力がある背後の或る大きな力に、私はこれまで恐れをなし、じっと我慢をしてきた。しかしこのことは、一度は白日の下にさらされなければならない。自由主義や民主主義、人権の保障、司法権の独立ないし裁判官の地位の保障といっても、理屈と実際では雲泥の差があるのである。私はここに意を決して、本件第一・二審の裁判官をも違法な裁判に追いこんだ或る力の排除を提案する』(財田川暗黒裁判より)
○これはつまりこうだ。田舎の元判事の分際でありながら、最高裁まで行って極刑が確定されたこの事件を誤判であると主張し、そればかりか警察官と検事の犯罪性まで立証するとは何事か、身の程をわきまえろという「或る力」からのシグナルであったと考えられる。
*
昭和50年「財田川暗黒裁判・矢野伊吉=著」発売。
昭和56年 高松地裁、再審を開始。
昭和58年 矢野伊吉、死去(享年71)。
昭和59年 被告人=谷口繁義、無罪確定。
平成17年 谷口繁義、死去(享年74)。

獄中の谷口繁義が描いて贈った"聖母マリヤ像"を手にする矢野伊吉弁護士(昭和47年撮影)。