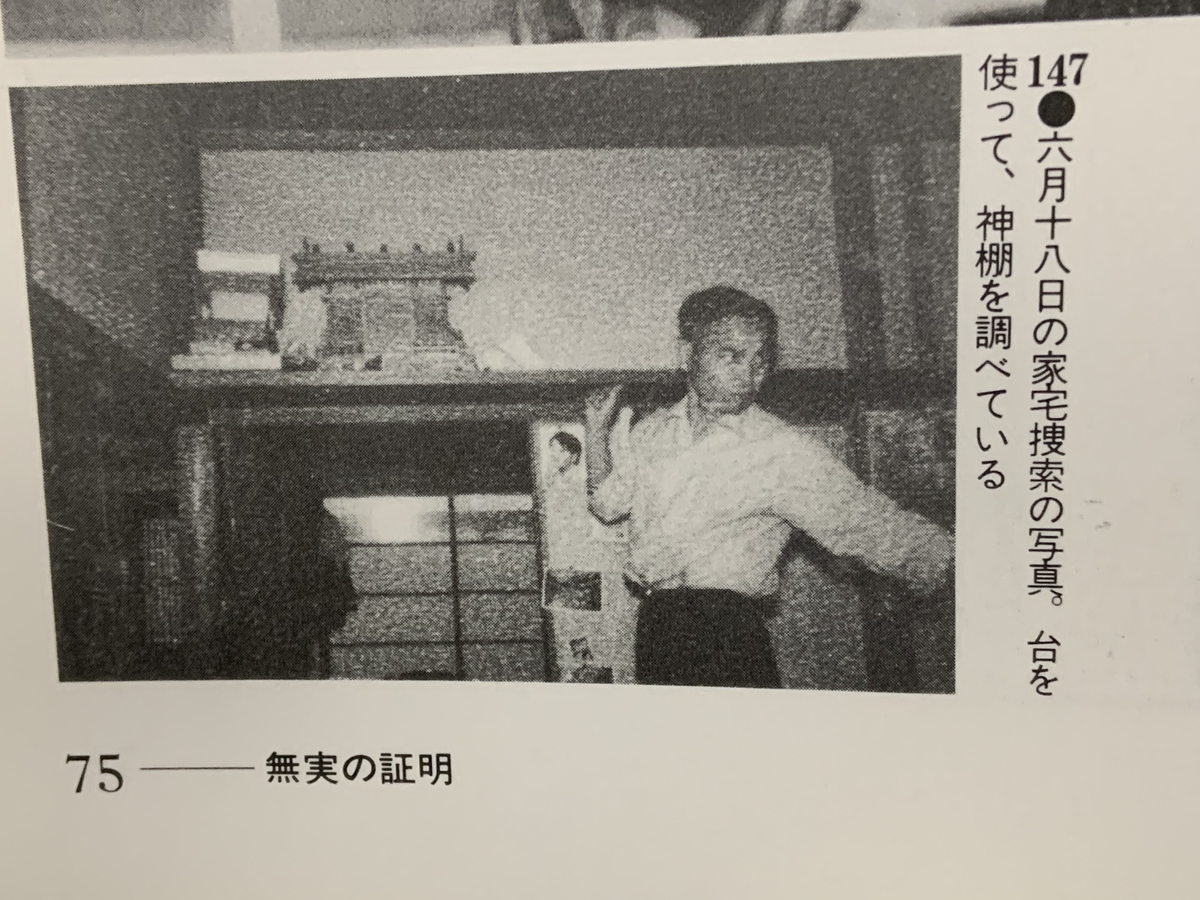狭山の黒い闇に触れる 83
昨日の続きである。小島朝政証人( 埼玉県浦和警察署次席 五十歳 )が、石川被告宅における家宅捜索において、証拠品である万年筆を兄に発見させた行為を指摘され、「私のほうから、先に発見するのが常道だと、こうおっしゃるんですか」と、やや驚嘆気味に逆質問しているが、私は(その通り、あなたが先に発見するのだ)と心で思いながら続きを読むと、さすが弁護人、「そうです」と即答。しかし証人は「いや、そういうこともありません」と強情を張る。弁護人:「いや、こういうことなんですよ、証人はまあ、自供に基づいて捜しに行くんだからということを先ほど来強調されるのですが、まあそうであったとしても、その自供に基づくという万年筆の所在場所それから万年筆の置いてあった状態、それから、まあ、ほこりの積もった状態とか、それらを捜査官がまず目に入れる必要があるのではないかと、一般的に考えていかがでございますか」緩急をつけながらの弁護人の問いに証人は「むしろ私の手から見るより(原文ママ)第三者の手から出たほうが、その場合効率的であったということと正確であるというふうに考えたからそうやりましたつまり、三人の捜査員で部屋の中を端々捜したってとても捜しきれるものではないと」と述べる。私は今、この公判調書を読んでいて問いと答えに微妙な誤差が感じられ、それとは一体なんだろうかと考える。質問の真意が証人に伝わらないのか。あるいは証人が的を得た返答をしており、弁護人たち、または私のような者の側が理解不足であるのか、いずれにせよこの万年筆の発見のしかたについて法廷で問答が繰り返されてゆく。