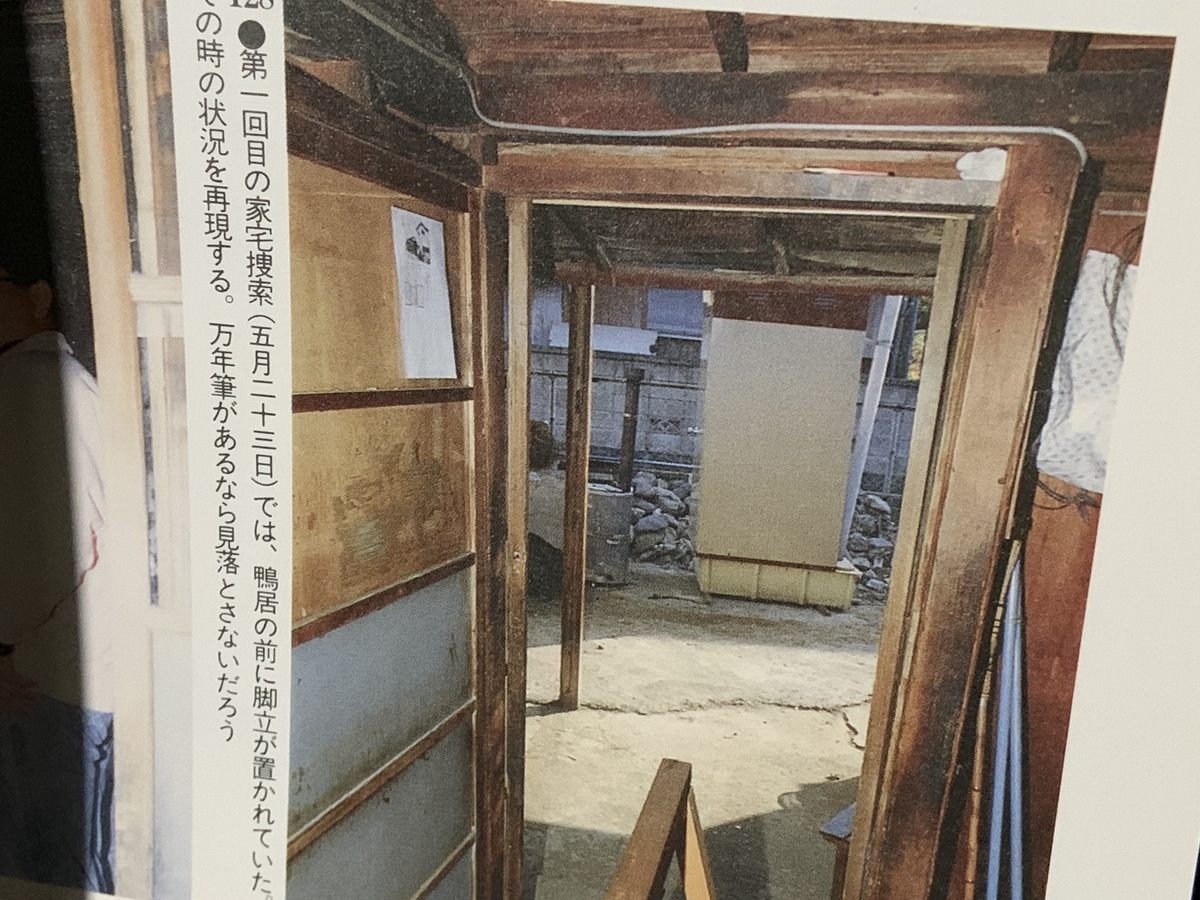狭山の黒い闇に触れる 77
橋本弁護人:「現場から万年筆を取り出す前に、万年筆がどういう状況で、どういうふうに置かれてあるかというような点については調べてみましたか」証人:「それは全然見ておりませんでした」弁護人:「万年筆に犯人の指紋が付着しておるというようなことは十分考えられるわけですね」証人:「はい」弁護人:「捜査官として」証人:「はい」弁護人:「従って万年筆を現場から取り出すには十分注意を要することだと思いますけれども、そういう点の注意は十分与えた上で捜してもらったんですか」証人:「そのような注意は与えておりません、なぜならば、この捜索はですね、すでに当時被疑者が自供したことによって行われた捜索差押でありまして、相当の日時も経過しておると、あまつさえまあ場所が今申し上げました、かもじ(鴨居:筆者注)のような所にあると、もう指紋も期待できないと、こういうふうに考えておりましたから、これは、先生ご承知と思いますが、万年筆のようにもう極端にさわったところのものには指紋が検出されないと、こういうのが私達捜査の場合多いわけでございます。そのような意味から指紋というようなことはあてにしておりませんでした」(609丁下段から610丁上段より抜粋)。私には昭和三十年代の警察が科学捜査に関してどれ程の技術を持っていたか判らない。現代の科学捜査技術と比べると、当然それは劣っていたであろう。逆に技法の選択肢が少ない分、証拠物の鑑定に時間をかけ十分吟味した上で結論を出せるとも言えよう。それを怠った捜査が冤罪を生むわけだ。とすれば小島朝政証人の言う「極端にさわった万年筆」からは「指紋が検出されない」「指紋(検出)は、あてにできない」といった結論ありきの捜査方法は完全に間違っていると言えよう。むしろ、検出されては困る指紋が付着していた可能性が考えられると私は睨んでいるが・・・おや、つい、口がすべってしまったな。